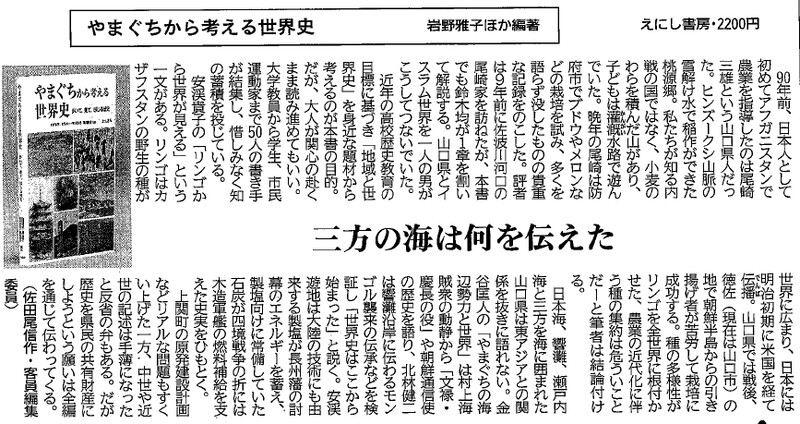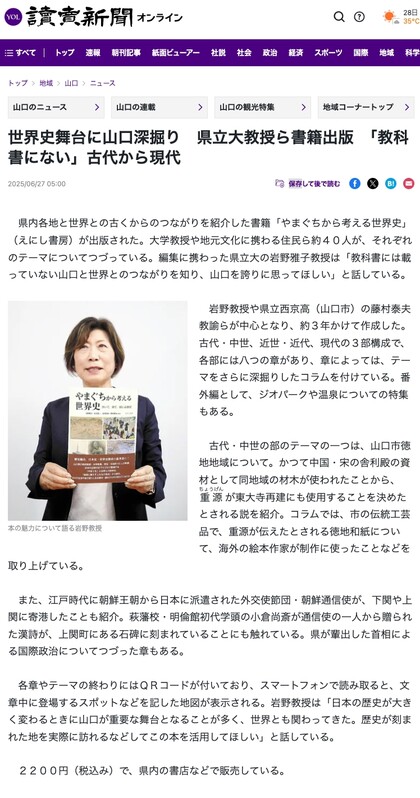![]()
書評)「やまぐちから考える世界史」佐田尾信作氏評
2025/06/15
中国新聞 2025年6月15日朝刊に 掲載されました。
高く評価していただき、光栄に存じます。
やまぐちから考える世界史
えにし書房・2200円
岩野雅子ほか編著
三方の海は何を伝えた
30年前、日本人として初めてアフガニスタンで農業を指導したのは尾崎三雄という山口県人だった。ヒンズークシ山脈の雪解け水で稲作ができた桃源郷。私たちが知る内戦の国ではなく、小麦のわらを積んだ山があり、子どもは水路で遊んでいた。晩年の尾崎は防府市でブドウやメロンなどの栽培を試み、多くを語らず没したものの貴重な記録をのこした。評者は9年前に佐波川河口の尾崎家を訪ねたが、本書でも鈴木が1章を割いて解説する。 山口県とイスラム世界を一人の男がこうしてつないでいた。
近年の高校歴史教育の目標に基づき「地域と世界史」を身近な題材から考えるのが本書の目的。だが、大人が関心の赴くまま読み進めてもいい。大学教員から学生、市民運動家まで50人の書き手が結集し、惜しみなく知の蓄積を投じている。
安渓貴子の「リンゴから世界が見える」という一文がある。リンゴはカザフスタンの野生の種が世界に広まり、日本には明治初期に米国を経て伝播。山口県では戦後、徳佐(現在は山口市)の地で朝鮮半島からの引き揚げ者が苦労して栽培に成功する。種の多様性がリンゴを全世界に根付かせた。農業の近代化に伴う種の集約は危ういことだ––と筆者は結論付ける。
日本海、響灘、瀬戸内海と三方を海に囲まれた山口県は東アジアとの関係を抜きに語れない。金谷匡人の「やまぐちの海辺勢力と世界」は村上海賊衆の動静から「文禄・慶長の役」や朝鮮通信使の歴史を語り、北林健二は響灘沿岸に伝わるモンゴル襲来の伝承などを検証し「世界史はここから始まった」と説く。安渓遊地は大陸の技術にも由来する製塩が長州藩の討幕のエネルギーを蓄え、製塩向けに常備していた石炭が四境戦争の折には木造軍艦の燃料補給を支えた史実をひもとく。
上関町の原発建設計画などリアルな問題もすくい上げた一方、中世や近世の記述は手薄になったと反省の弁もある。だが歴史を県民の共有財産にしようという願いは全編を通じて伝わってくる。
(佐田尾信作・客員編集委員)
引用終わり
佐田尾さんは、中国新聞を定年で退職されてからもジャーナリストとして健筆を振るっておられます。以下のようにご活躍です。
日本ペンクラブ会員
中国新聞客員編集委員
宮本常一記念館運営協議会委員
広島民俗学会理事
6/27 讀賣新聞にも紹介されました。