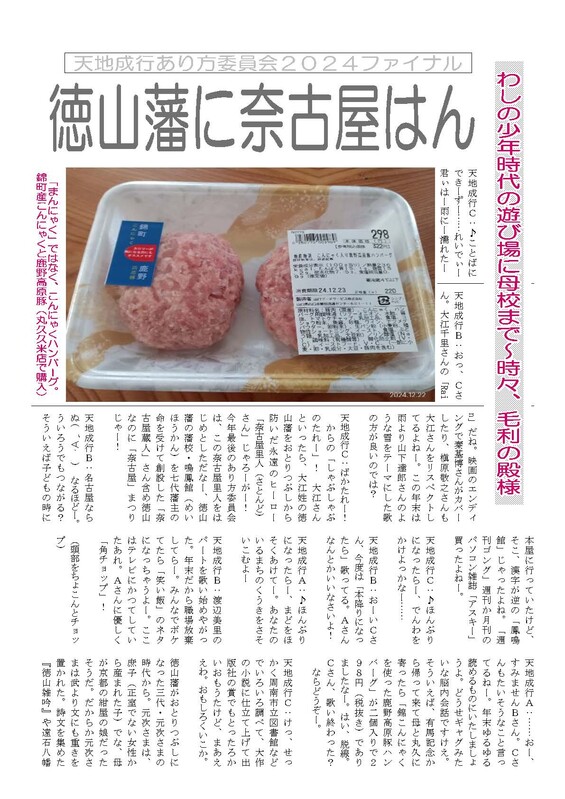![]()
#天地成行 #ありかた委員会)こんにゃくハンバーグを食べながら #万役山事件 を思う #周南市
2024/12/24
天地成行さんが、山口県周南市の江戸時代の郷土の偉人に取材した脳内会話の「あり方委員会」の記録を2024年のしめくくりとして発表されました。
掘ればでてくる宝の泉。急ぎすぎて体が埋まらぬように気をつけながらほりおこし。そうやってゆるゆると掘りさげた結果を一般大衆向けに広める試みです。
さて、天地成行ファンクラブの私(安渓遊地)はといえば、昨年から、江戸時代の文人と漢詩についての本をいくつか読みました。
まずは、朝鮮通信使の旅の記録である、申愈翰(しん・ゆはん)著『海游録』(平凡社・東洋文庫)。李氏朝鮮時代の紀行文学の双璧といわれるもののひとつです。そこに出てくる二人の独学の知の巨人のことを読み進めました。将軍たちの知恵袋として働いた大学者の二人でしたが、同時代の学者としては互いにおりあいがひどく悪かったのですね、この二人は。
吉川幸次郎先生(https://ankei.jp/yuji/?n=1694)に、徂徠豆腐 の落語で有名な学者・荻生徂来をとりあげた「徂徠学案」という文章があります。一冊にまとめられた本の1章なのですが、1章を読み通すだけでも、相当の根気を要するものです。ひとりの学者の知的冒険の行方が、学者の押さえた筆の運びから伝わってきて背中が暖かくなる思いです。(松岡正剛さんの千夜千冊でも紹介されています。https://1000ya.isis.ne.jp/1008.html)
新井白石の「折たく柴の記」も、桑原武夫さんの現代語訳で通読しました。
こんな本を読む機会にめぐまれたのは、高校生向けの歴史副読本『やまぐちから考える世界史』(えにし書房)の編集と執筆のお手伝いをしているからなのです。2025年4月以降の発売をめざしてただいま校正中ですが、部分的にお目にかけておきましょう。下線の部分は、スペースの都合で割愛しましたので、ここだけの公開です。
3. 朝鮮通信使にほめられて出世
新井白石(1657–1725)は、6代将軍・家宣に重用され、進講役として「正徳【しょうとく】の治」と呼ばれる善政を支えました。イタリア人宣教師シドッチの尋問を担当して『西洋紀聞』の記録を残した彼は、30歳までは独学でした。幕府に登用されたのは、通信使3人に詩集への序文や跋【ばつ】文を書いてもらった『白石詩草』が朱子学者の木下順庵【じゅんあん】(1621–1699)に見出されたのがそもそものきっかけでした(新井、2004)。
申愈翰は『海游録』の中で、熱心な割には日本人のつくる詩については、中国語の音韻が分かっていないために笑うしかないものが多い、と率直に述べています。1764(宝暦14)年の朝鮮通信使の正使書記であった成龍淵は、「ふりがなのない漢文を書くという一点だけでも、荻生徂来【おぎゅうそらい】がいかにすぐれた学者だったかわかる」と述べました。
幕府伝統の朱子学に対して、古文辞学を確立して、本居宣長(1730–1801)や、ずっと後の津和野出身の啓蒙家・西周【にしあまね】(1829–1897)にまで影響を与えた荻生徂来(1666–1728)は、落語「徂来豆腐」にも登場する、よく知られた学者です。彼は、独学であったために、中国語をそのまま読むことができるようになったのです。徂来の弟子で、萩の明倫館の二代目学頭を務めることになる、山県周南【やまがたしゅうなん】(1687–1752)は、その詩の才能を朝鮮通信使に激賞され、とくに、正使へのお目通りを許されています。この評価によって、周南の師である徂来自身の名声も江戸で高まりました。
このように、朝鮮通信使との詩の交流を契機に、学者として幕府に登用された例があることを見逃すことはできません。明倫館初代学頭の小倉尚斎も、申愈翰がその学問と人柄を高く評価したひとりでした。彼も幕府に招かれましたが、子どものころから足が不自由だったためか、病気を理由にこれを辞退しています。
申愈翰は、科挙による試験に合格して抜擢された経験から、まことにつまらぬ人物が世襲だからというだけで威張っている当時の日本の嘆かわしい状況について、対馬藩主を手始めにこきおろす記述をしています。一方で科挙による弊害についても書いていて、朝鮮では試験勉強のために剽窃【ひょうせつ】(模範解答のコピペか)が横行しているが、日本人の文章は、短いなかにも独自のきらめきがあると述べました。
筆者は、高校で白居易の専門家の武部利夫先生(1925–1981)から、漢文を3年間習いました。あるとき、武部先生は、杜甫の「春望」の詩を、四声のある中国語の発音で朗唱してくださいました。返り点などを打って、日本語の語順に合わせて読んでいるだけでは、漢詩の魅力は半分も伝わらないのだというメッセージだったのでしょう。
1719年8月18日、対馬・壱岐・九州を経由した朝鮮通信使の一行は、絢爛たる船の出迎えを受けて、赤間関【あかまがせき】(しものせき)に到着します。対馬藩の通訳官として雨森芳洲【あめのもりほうしゅう】(1668–1755)が同行してきていました。対馬に朝鮮との友好親善のための通訳の学校を作った、当時の国際交流の最先端にいた人物です。江戸後期の『先哲叢談』には、朝鮮の文人が雨森芳洲に「あなたは、いろいろな国の言葉がお上手ですが、特に日本語がお上手(君善操諸邦音、而殊熟日本)」と冗談を言ったとあります(原、1816)。2人は外交上の行き違いなどで衝突もしましたが、申愈翰は、江戸で雨森芳洲と同門の新井白石に面会した折に、これほどの人材をなぜ幕府が登用しないのかと尋ねました(申、1974)。
この時の通信使一行が、京都の方広寺での饗宴という予定に異議を唱えて、外交上のもめごとに発展しました。「国家安康の鐘」で知られる方広寺(大仏殿)は、秀吉が建てさせた寺で、しかも門前に秀吉の軍勢が朝鮮で殺した人々の鼻や耳を切り取って持ち帰った「耳塚」があります(コラム「倭徳山・鼻塚・地蔵墓」参照)。そのような所には行かないという朝鮮側の拒絶に対して、日本側は家康の時代に建てたものだという文書を示したり、「耳塚」が見えないように幕を張るなど働きかけて、最終的には実施されるのですが、申愈翰は、その交渉の最前線に立たされた雨森芳洲が、大声で叫んだりして取り乱すようすを書いています(申、1974)。実は、雨森自身は、方広寺訪問には反対であったのに、仕事柄それを朝鮮側に押し付ける仕事をさせられたというのが実情であったといいます。
こうした対立もありましたが、対馬での最後の別れに際して、雨森芳洲が「すでに老いた自分はこんな辺境の地で朽ち果てるが、あなたはお国に帰って偉くなられてください」と告げ、さめざめと涙を流して別れを惜しんだと、申愈翰は長旅をともにした好敵手との人間的な交流を書き残しています(申、1974)。
天地と遊地 地域の歴史ほりおこし隊からのお知らせでした。
参考文献
新井白石・桑原武夫訳(2004)『折たく柴の記』中央公論社。
下関市立長府博物館(1996)『特別展・東アジアの中の下関――近世下関の対外交渉』下関市立長府博物館。
申愈翰・姜在彦訳注(1974)『海游録――朝鮮通信使の日本紀行』平凡社。
鄭敬珍(2016)「一七六四年の朝鮮通信使からみる庶孼文人」『日本研究』 52: 151–181。
仲尾宏(2007)『朝鮮通信使――江戸日本の誠信外交』岩波書店。
ウェブサイト
岩下昭弘編(2012)「特集:国境(くにざかい)フォーラム in 隠岐」『ライブ・イン・ボーダースタディーズ』11 https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/BorderStudies/essays/live/pdf/Borderlive11-oki.pdf
加藤徹のホームページ https://www.isc.meiji.ac.jp/~katotoru/
佐々木平太夫・申愈翰(1720)『両関唱和集』国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/1226870.html
原念斎(1816)『先哲叢談』国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1224563.html