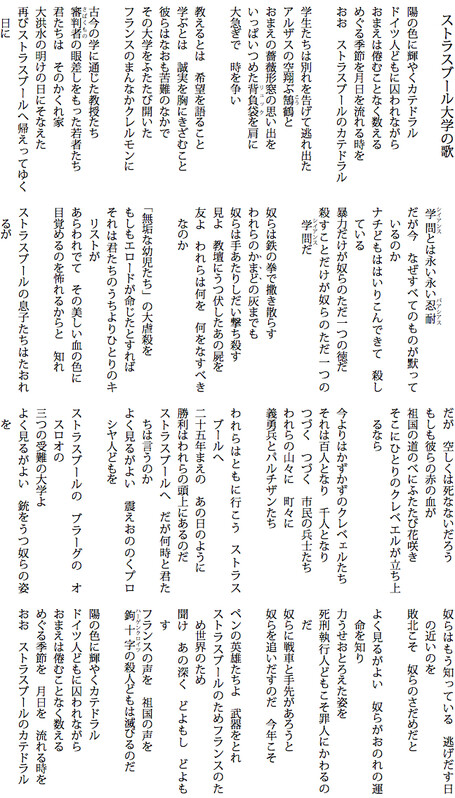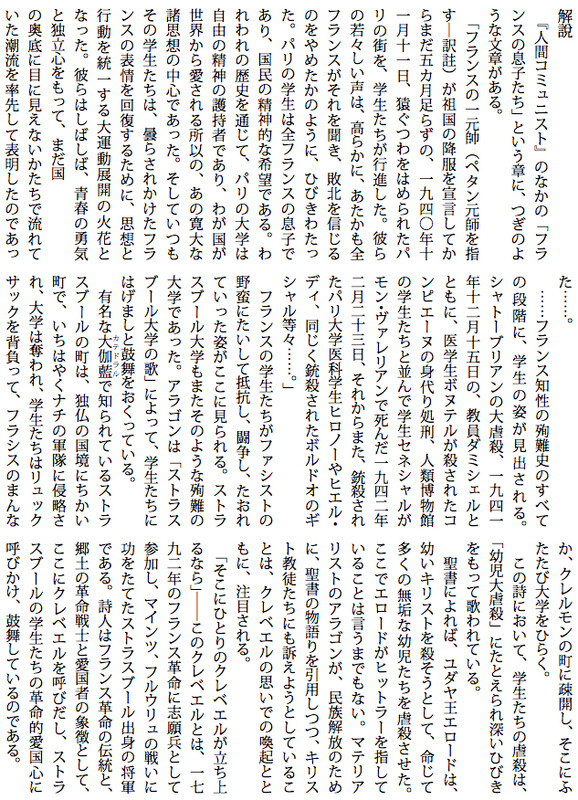![]()
ルイ・アラゴン)ストラスブール大学の歌 教えるとは 希望を語ること
2024/09/16
https://oshimahakkou.blog.fc2.com/blog-entry-6046.html からの引用です。
ストラスブール大学の歌
ルイ・アラゴン
陽の色に輝やくカテドラル
ドイツ人どもに囚われながら
おまえは倦むことなく数える
めぐる季節を月日を流れる時を
おお ストラスブールのカテドラル
学生たちは別れを告げて逃れ出た
アルザスの空翔ぶ鵠《こう》鶴と
おまえの薔薇形窓の思い出を
いっぱいつめた背負袋《リュック》を肩に
大急ぎで 時を争い
教えるとは 希望を語ること
学ぶとは 誠実を胸にきざむこと
彼らはなおも苦難のなかで
その大学をふたたび開いた
フランスのまんなかクレルモンに
古今の学に通じた教授たち
審判者《さばくもの》の眼差しをもった若者たち
君たちは そのかくれ家
大洪水の明けの日にそなえた
再びストラスブールへ帰えってゆく日に
学問《シイアンス》とは永い永い忍耐《パアシアンス》
だが今 なぜすべてのものが默っているのか
ナチどもははいりこんできて 殺している
暴力だけが奴らのただ一つの徳だ
殺すことだけが奴らのただ一つの学問《シイアンス》だ
奴らは鉄の拳で撒き散らす
われらのかまどの灰までも
奴らは手あたりしだい撃ち殺す
見よ 教壇にうつ伏したあの屍を
友よ われらは何を 何をなすべきなのか
「無垢な幼児たち」の大虐殺を
もしもエロードが命じたとすれば
それは君たちのうちよりひとりのキリストが
あらわれでて その美しい血の色に
目覚めるのを怖れるからと 知れ
ストラスブールの息子たちはたおれるが
だが 空しくは死なないだろう
もしも彼らの赤の血が
祖国の道のべにふたたび花咲き
そこにひとりのクレベエルが立ち上るなら
今よりはかずかずのクレベェルたち
それは百人となり 千人となり
つづく つづく 市民の兵士たち
われらの山々に 町々に
義勇兵とパルチザンたち
われらはともに行こう ストラスブールへ
二十五年まえの あの日のように
勝利はわれらの頭上にあるのだ
ストラスブールへ だが何時と君たちは言うのか
よく見るがよい 震えおののくプロシヤ人どもを
ストラスブールの ブラーグの オスロオの
三つの受難の大学よ
よく見るがよい 銃をうつ奴らの姿を
奴らはもう知っている 逃げだす日の近いのを
敗北こそ 奴らのさだめだと
よく見るがよい 奴らがおのれの運命を知り
力うせおとろえた姿を
死刑執行人どもこそ罪人にかわるのだ
奴らに戦車と手先があろうと
奴らを追いだすのだ 今年こそ
ペンの英雄たちよ 武器をとれ
ストラスブールのためフランスのため世界のため
聞け あの深く どよもし どよもす
フランスの声を 祖国の声を
鉤十字《ハーゲンクロイツ》の殺人どもは滅びるのだ
陽の色に輝やくカテドラル
ドイツ人どもに囚われながら
おまえは倦むことなく数える
めぐる季節を 月日を 流れる時を
おお ストラスブールのカテドラル
解說
『人間コミュニスト』のなかの「フランスの息子たち」という章に、つぎのような文章がある。
「フランスの一元帥(ペタン元師を指す─訳註)が祖国の降服を宣言してからまだ五カ月足らずの、一九四〇年十一月十一日、猿ぐつわをはめられたパリの街を、学生たちが行進した。彼らの若々しい声は、高らかに、あたかも全フランスがそれを聞き、敗北を信じるのをやめたかのように、ひびきわたった。パリの学生は全フランスの息子であり、国民の精神的な希望である。われわれの歴史を通じて、パリの大学は自由の精神の護持者であり、わが国が世界から愛される所以の、あの寛大な諸思想の中心であった。そしていつもその学生たちは、曇らされかけたフランスの表情を回復するために、思想と行動を統一する大運動展開の火花となった。彼らはしばしば、青春の勇気と独立心をもって、まだ国
の奥底に目に見えないかたちで流れていた潮流を率先して表明したのであった……。
……フランス知性の殉難史のすべての段階に、学生の姿が見出される。シャトーブリアンの大虐殺、一九四一年十二月十五日の、教員ダミシェルとともに、医学生ボヌテルが殺されたコンピエーヌの身代り処刑、人類博物館の学生たちと並んで学生セネシャルがモン・ヴァレリアンで死んだ一九四二年二月二十三日、それからまた、銃殺されたパリ大学医科学生ヒロノーやヒエル・ディ、同じく銃殺されたボルドオのギシャル等々……。」
フランスの学生たちがファシストの野蛮にたいして抵抗し、闘争し、たおれていった姿がここに見られる。ストラスブール大学もまたそのような殉難の大学であった。アラゴンは「ストラスブール大学の歌」によって、学生たちにはげましと鼓舞をおくっている。
有名な大伽藍《カテドラル》で知られているストラスブールの町は、独仏の国境にちかい町で、いちはやくナチの軍隊に侵略され、大学は奪われ、学生たちはリュックサックを背負って、フラシスのまんなか、クレルモンの町に疎開し、そこにふたたび大学をひらく。
この詩において、学生たちの虐殺は、「幼児大虐殺」にたとえられ深いひびきをもって歌われている。
聖書によれば、ユダヤ王エロードは、幼いキリストを殺そうとして、命じて多くの無垢な幼児たちを虐殺させた。ここでエロードがヒットラーを指していることは言うまでもない。マテリアリストのアラゴンが、民族解放のために、聖書の物語りを引用しつつ、キリスト教徒たちにも訴えようとしていることは、クレベエルの思いでの喚起とともに、注目される。
「そこにひとりのクレベエルが立ち上るなら」――このクレベエルとは、一七九二年のフランス革命に志願兵として参加し、マインツ、フルウリュの戦いに功をたてたストラスブール出身の将軍である。詩人はフランス革命の伝統と、郷土の革命戦士と愛国者の象徴として、ここにクレベエルを呼びだし、ストラスブールの学生たちの革命的愛国心に呼びかけ、鼓舞しているのである。
関連記事
https://oshimahakkou.blog.fc2.com/blog-entry-6047.html
アラゴンの詩を胸に
片羽登呂平
今から五十五年前の一九五一年二月二十日に三一書房から発行されたアラゴンの『フランスの起床ラッパ』(定価一五〇円)は大島博光さんの翻訳で、私が大島さんの本に接した最初の著書だった。(付記・大島さんの翻訳で同じ題名で三一書房版に載っていない五篇の作品が加えられた本が一九八〇年に新日本出版社から文庫版で出版されている。)
三一書房版の特徴は作品のうしろに解説ふうに作品に即した大島さんの言葉が添えられ、「あとがき」として総括的に「アラゴンの道」と題して付された三十五頁の大島さんのエッセイは、レジスタンスの運動を全く知らない私には、そこに書かれている内容は海綿が水滴を余さず吸い取るように痩せこけた私の荒蕪地になだれ込んできた。
「一九五〇年頃、初めて『フランスの起床ラッパ』を読んで訳したときの、ほとんど衝撃的な感動をわたしは忘れることができない。詩がこれほどわたしを根底からゆさぶったことはなかった。わたしはそこに、美と真実とが、詩と伝説とが、そして詩と歴史とが、みごとに結びつき、とけあった詩的奇跡をみる想いがした。」(文庫版「解説」から)
「ほとんど衝撃的な感動」と大島さんは述べているが、私には異文化の世界から受けた感動の渦の連鎖で、〈薔薇と木犀草〉を読んだときの感動はひときわ激しいものだった。
神を信じたものも
信じなかったものも
という二行のリフレーンに挟まれて四行の詩行を置いた六十四行の〈薔薇と木犀草〉はレジスタンス詩の神髄を波打たせ、太平洋戦争の中で盲目的な生活に明け暮れていた私には絶え難い衝撃だった。
大島さんのこの詩の解説は「ナチのむごたらしい斧のもとにたおれていったのは、ひとりコミュニストばかりではなかった。多くのカトリック教徒もいた。自由主義者もいた。ゴオル主義者もいた。その思想と信仰の如何を問わずそれらのひとびとは祖国フランスとその自由と正義とを愛しまもるために、たたかいたおれていったのだ。ナチの野蛮な侵略から、祖国と自己とを解放するために、すべてのひとびとが、その思想や党派を超えて、フランスという名まえのもとに腕を組み、人間性の名のもとにその行動を統一しなければならなかった。/そのとき、アラゴンは、その詩的手法を、うけ継がるべき伝統の縦の糸から新しくつむぎだしたように、また血と人間性の横の糸によって、ひとびとをむすびつける、共同の闘いへの讃歌を、うつくしく歌わないではいられなかった。ナチの銃口のまえでともにたおれたコミュニスト、ガブリエル・ペリとギイ・モケーおよびカトリック教徒エッティアンヌ・ドォルヴとジルベェル・ドリュに、同時に捧げられている詩『薔薇と木草』がそれである。/かって、祖国への愛と、そのためにたおれていった英雄たちへの愛とが、このように美しく歌われたことは稀れだ。この詩の美しさと深さは、またほかならぬアラゴン自身の人間コミュニストとしての愛の深みから生れ、そこか鳴りひびいてきているのだ。」
一九五〇年八月に詩を書く仲間と語らって「新岩手詩人集団」を結成し機関紙「氷河期」を発行、この年を境にメーデー事件、朝鮮戦争勃発、警察予備隊令公布、翌年には講和条約、日米安保条約の締結と政治、軍事の動きが慌ただしく、私が大島さんのアラゴンに接した時期は、それを咀嚼しなければならない条件と重なっていたのだと今は思わないわけにはいかない。「氷河期」に朝鮮戦争に手出ししているアメリカ批判の詩を数多く書き、政令三二五号(占領政策違反)容疑で重労働を喰らうと周囲に脅かされたり、一九五二年には大島さんが主宰する『角笛』の復刊に同人として参加したり、五十年を超える大島さんとの交際だったが、大島さんの葬儀に顔も出せず、二年ほど前から読み書きに難渋する病臥輾転の低落生活、記憶や資料を洗い出して書くべきことをきちんとという思いばかりで、アラゴンの詩が大きく私に転機をもたらしてくれたと「フランスの起床ラッパ」を胸に置いて、いまは大島博光さんに敬礼するばかりである。
(ミニエッセイ「大島博光さんとわたし」『詩人会議』二〇〇六年八月)
以下は、訳者の解説です。
https://oshimahakkou.blog.fc2.com/blog-entry-6055.html
『フランスの起床ラッパ』(新日本文庫) 解説
2024/09/15(日)
解 説
大島博光
一九五〇年頃、初めて『フランスの起床ラッパ』を読んで訳したときの、ほとんど衝撃的な感動をわたしは忘れることができない。詩がこれほどわたしを根底からゆさぶったことはなかった。わたしはそこに、美と真実とが、詩と伝説とが、そして詩と歴史とが、みごとに結びつきとけあった詩的奇跡をみる想いがした。「ガブリエル・ペリの伝説」を、小さな集会などで、わたしはすすんで朗読したりした……
『フランスの起床ラッパ』は、アラゴンがレジスタンスのなかで、主として一九四二、三年頃に書いた有名な詩篇を集めた詩集で、それがパリに現われたのは、一九四四年十二月であった。その八月には、ナチス・ドイツ軍の占領による長い地獄の夜からパリは解放されていた。この詩集はたちまちひろい読者を獲得し、フランスの詩の歴史上かつて見ないような成功を収めた。詩がこのような広範な大衆に迎えられたのは、ヴィクトル・ユゴーの『懲罰詩集』以来のことだったともいわれている。
まず、この詩集が書かれた頃の歴史的背景を大まかに見ておこう。
一九三九年九月、フランスはイギリスとともにヒットラーのドイツに宣戦を布告したが、早くも一九四〇年六月には一敗地にまみれ、ペタン政府は独仏休戦条約に調印する。この時をさかいに、公然とした国家間の戦争、古典的な戦争の段階は終りを告げ、それ以後は、人民の戦争、義勇兵による国民の戦争、つまり対独抵抗《レジスタンス》の闘争が始まる。レジスタンスは種類のちがうもうひとつの戦争であった。つぎにその期間における主な出来ごとを列挙しておこう。
一九四〇年十一月十一日(第一次大戦休戦記念日)、最初の公然たる反独デモンストレーションがパリの学生たちによってエトワール広場で決行された。多くの犠牲者たちの血が流されたが、それはレジスタンスの最初の火の手となる。
一九四一年五月、ドイツ占領軍による銃殺と流刑に抗して、パ・ド・カレの炭坑労働者十万は数週間にわたるストライキ闘争を行なう。
一九四一年八月二十一日、共産党員ファビヤン大佐は地下鉄バルベ駅で白昼ドイツ軍将校をピストルで射殺する。それはレジスタンスにおける武装闘争の最初の合図となる。
一九四一年十月二十二日、西仏ナントに近いシャトーブリアンにおいて二十七名の人質が銃殺される。
一九四一年十二月十五日、パリ西南郊モン・ヴァレリアンにおいて、ガブリエル・ペリをふくむ一〇〇名の人質が処刑される。
一九四二年二月二十三日、二十五日、「人類博物館」の学者グループがモン・ヴァレリアンにおいて銃殺される。
一九四二年五月、ジャック・ドクール、ジョルジュ・ポリッツェルたち、非合法誌「自由思想」のグループがモン・ヴァレリアンで銃殺される。八月アラゴンは「詩法」のなかで「五月の死者たち、わが友らのために/いまよりはただ彼らのために」とうたう。
この年、ナチはフランス青年を徴用してドイツの工場に送る政策を強めたため、多くのフランス青年は徴用を忌避して、マキ団やパルチザン部隊に参加する。
一九四三年二月二日、スターリングラードにおけるドイツ軍の壊滅は、ナチス・ドイツの敗北を避けられないものにする。
この頃、フランス占領中のドイツ軍はいよいよファシストの本性を発揮し、掠奪、虐殺をほしいままにする。しかし、イツ占領軍とヴィシィ政府の「民警隊《ミリス》」との残酷な弾圧に抗して、パルチザン部隊によるゲリラ戦はますます活発となる。
一九四三年五月、すべての抵抗組織および諸政党を網羅した「レジスタンス国民会議」が創設される。
一九四三年十一月、クレルモン・フェランにおいてストラスブール大学の教授、学生が銃殺され、数百名が逮捕される。
一九四四年二月─四月、南部山岳地帯に陣どるマキ(パルチザン)を鎮圧するため、ドイツ占領軍とヴィシィ政府は凄惨な闘いをくりひろげる。
一九四四年六月十日、中部フランス、リモージュに近いオラドゥール・シュール・グラーヌにおいて、婦人と子供たちが教会につめこまれて生きながらに焼き殺される。村は一挙にして地上から抹殺される。
一九四四年八月十九日、パリは自力で武装蜂起をはじめ、「国内フランス軍」は戦闘を全市に展開する。
一九四四年八月二十五日、パリはみずからを解放する。
さて、このような状況のなかで、アラゴン自身はどうしていたかを見てみよう。──一九三九年九月、戦争勃発とともに、フランス共産党は解散させられ、アラゴンの編集していた「ス・ソワール」紙は発行禁止になる。アラゴンは動員されて、愛する妻エルザと別れて入隊する。詩人はその頃の悲痛な思いを「ひき裂かれた恋びとたち」(『断腸詩集』)のなかに歌いあげる。
駅で つんぼ盲目《めくら》の人たちが その暗い心の叫びを
悲壮な身ぶり手ぶりで 話し合うように
ひき裂かれた恋びとたちも 狂おしい仕ぐさをする
冬と武器との 白じらとした静けさのなかで
……
(飯塚書店『アラゴン選集』第一巻一八二ページ)
当時、戦争によってひき裂かれていたのは、恋びとたちや夫婦ばかりではなく、「ス・ソワール」紙の最後の集会に集まった進歩的な知識人や同志たちも、動員されて散りぢりになり、フランスのどこかで、見知らぬひとたちの中で、「駅で話し合っているつんぽ盲目の人たち」のような自分を見出していたのである。
一九四〇年六月、ベルギーに派遣されていたアラゴンの部隊は反撃されて、有名な「ダンケルクの悲劇」に遭遇し、アラゴンはからくも九死に一生をえて帰還する。七月に動員を解除されて、かれはエルザと再会し、ひとまず西南仏カルカソンヌに落ちつく。
この頃、フランス共産党は地下に追いやられていて、アラゴンが党と連絡をもちつづけていたとは考えられない。彼はひとりで、詩の方向を決め、方針をたて、いろいろな出版との協力を決めていた。その頃は、混乱、不安、動揺がフランスじゅうを蔽っており、誠実な人たちさえ、どうしていいか分からず、途方にくれていた。
アラゴンは詩によってそれらの人たちにたたかいの道をさし示し、希望をかかげてはげました。その典型として、例えば「荊の冠」(『断腸詩集』)のような詩をあげることもできよう。
一九四一年には南仏ニースに滞在して、詩による抵抗運動をすすめると同時に、レジスタンスの文学者の組織として「全国作家委員会」を創設する。
一九四二年十一月十一日、ニースにイタリア軍が侵入してきたため、アラゴン夫妻はニースを離れてドロームに移り、いよいよ地下の生活が始まる。このドロームの家についてエルザはのちに書く。
「隠れ家は、ディウルフィの上方の、山の中にあって、そこへ辿りつくには歩いてゆくよりほかなかった。わたしたちはこの隠れ家を陰謀めかしく『天国』と呼んだ。それは、三つの村をむすぶ四つ辻にぽつんと立った廃屋《あばらや》だった。だから、三つの村のどれにぞくするのか、はっきりとはわからなかった。まるでだれも気にとめないような家だった……」
この「天国」は安全な隠れ家ではあったが、山の中にあったため地下活動をつづけるのに不便でもあり不可能でもあった。そこでアラゴン夫妻は、リヨンのモンシャにある、友人のルネ・タヴェルニエの家の屋根裏部屋を借りることになる。一九四三年一月の初めから六月末まで、そこに滞在する。その頃の思い出を、サドゥールはつぎのように書く。
「わたしは連絡のためにしばしばリヨンへ行って、このモンシャの別荘の屋根裏部屋を訪れた。そこでエルザは、『白い馬』や『アヴィニョンの恋人たち』の原稿をよんでくれた。アラゴンは、その頃マキ団を組織した人たちを讃えて、『たたかう百の村』をそこで書いた。
リヨンの町を見おろすモンシャの小さな辻公園で、かれは『幸せな愛はどこにもない』をわたしに読んでくれた。それを聞いてわたしは泣いてしまった。この詩がひどく絶望的に思えて、この詩を発表しないようにわたしはかれに頼んだ。(その頼みはむだでもあり、まちがってもいた)」
『責苦のなかで歌ったもののバラード』もこの頃リヨンで書かれた。このガブリエル・ペリの不屈のたたかいを歌った詩は、だれが書いたのかも知られずに、コッピーされては人の手から手へと渡り、牢獄のなかにまで持ちこまれ、いつか作者のアラゴン自身のところにまで廻ってきたのだった。
しかしリヨンはますます危険になってきたので、アラゴン夫妻はモンシャ滞在六ヵ月ののち、ふたたび安全な隠れ家をもとめて、霧のなかに姿を消してゆく。こんどの隠れ家はサン・ドナという南仏ドゥローム県のまんなかの小さな村にあった。街道から遠く離れた、ぶどう畑や森や丘のある小さな村であった……
それからおよそ一年後、一九四四年八月二十四日、暑い夏の夜の十一時、ノートル・ダムの大鐘が突如として鳴り出した。つづいてパリじゅうの鐘という鐘が鳴り出した。星のまたたく夜空の下、燈火のない暗いパリは、夢のような歓喜の大合奏につつまれた……市民たちは外にとび出して街や大通りを埋めた。パリは解放された。いや、パリは連合軍の力をかりる前に、自力で、みずからを解放したのである。その歓喜をアラゴンは歌う。
勝利したわが人民のあの歓呼の声ほどに
わたしの心をうったものは かつてなかった
かくもわたしを歓《よろこ》ばせ 泣かせたものはなかった
経帷子《きょうかたびら》をひき裂くほどに 偉大なことはない
パリ パリ みずからを解き放ったパリよ
以上大ざっぱに見たように、対独抵抗《レジスタンス》とは、ナチス・ドイツの長靴とその傀儡《かいらい》ヴィシィ政府の裏切りによって奪いとられ踏みにじられた祖国を解放し、ナチの苛酷な圧制から人民を解放し、自由を奪いかえす闘いである。『フランスの起床ラッパ』はこの歴史的な闘いのなかで書かれ、この闘いをうたい、この闘いを反映している。「見捨てられた女」とはいうまでもなく祖国フランスを擬人化したものである。ヴィシィ政府は祖国をナチス・ドイツに売り渡したばかりでなく、ガブリエル・ペリを始め多くの愛国者を逮捕・密告によってナチに引き渡していたのである。
民族の独立と自由をめざすこの苛酷な闘いには、無数の英雄たちが必要であった。英雄たちは闘いのなかから、祖国フランスの奥深いところから立ち上ってきた。「ごく普通のフランス人がヘラクレスになった」のである。そのひとつの典型としてガブリエル・ペリが歌われる。ガブリエル・ペリが処刑の前夜に書いた最後の手紙は、自己自身への忠実さと未来への信頼にみちた遺言として有名であり、それは散文詩ともいわれる。
「ねがわくば、わたしがわが人生の理想に最後まで忠実だったことを、わが友人たちが知ってくれるように。ねがわくば、わたしがフランス万才!を叫んだゆえに死んでゆくということを、わが同胞たちが知ってくれるように。
わたしは最後にもう一度じぶんの良心をふりかえってみた。少しもやましいことはない。もしも、もう一度人生をやりなおさねばならぬとしても、わたしは同じ道を行くだろう。わたしは今夜もやはり信じている、『共産主義は世界の青春であり』そして『それは歌うたう明日《あす》の日を準備する』と言った、親愛なるポール・ヴァイヤン・クーチュリエの言葉の正しかったことを。わたしはまもなく『歌うたう明日《あす》の日』を準備するだろう。わたしは死に直面するだけの力をもちあわせているように思う。さようなら、フランス万才!」
そうしてアラゴンはペリの示した模範の意義について、つぎのように書く。
「一国の息子たちがどのような死に方をしうるかは重要なことだ。それはその国そのものの偉大さをはかる尺度ともなる。……ガブリエル・ペリは未来にとっても驚くべき、きわ立った姿を見せ、未来は彼のなかに二重の象徴を見るだろう。なぜなら、ペリは不屈な平和の戦士であると同時に、民族の名誉の守り手である。かれは人類をよりよくするために生命をささげた男であると同時に、侵略者の前に頭をさげるよりはその生命を与えたフランス人である。かれは民族の英雄であると同時に、全人類の英雄である……」(『殉難者たちの証言」)
「責苦のなかで歌ったもののバラード」「ガブリエル・ペリの伝説」のなかで歌われているのは、まさにこのようなペリのいさおしとその人間像なのである。
「薔薇と木犀草」にもまた、「ガブリエル・ペリとエッティアンヌ・ドォルヴへ/ギイ・モケーとジルベェル・ドリュへ」という獻辞が見られる。エッティアンヌ・ドォルヴ少佐はカトリックで王制主義者であった。彼はロンドンとの無線連絡の任に当っていたが、部下の裏切りによってドイツ軍の手に落ち、処刑された。
ジルベェル・ドリュはカトリックの学生で、一九四四年七月二十七日、リヨンのベルクール広場でドイツ兵によって銃殺された。死んだ彼のポケットからはアラゴンの『プロセリアンド』の小冊子がはみ出ていた。
ギイ・モケーは、一九四一年十月二十二日、シャトーブリアンで処刑された二十七名の人質のひとりで、まだ十七歳の共産党員の学生であった……
祖国と自由のために仆れたのは、ひとり共産党員ばかりではなく、多くのカトリック教徒も自由主義者もいたのである。この詩は、思想と信仰はちがっていても、ともに祖国解放のために仆れていった英雄たちと、その共同の闘いへの讃歌であり、ひろい統一行動への呼びかけとなっているのである。
「幸せな愛はどこにもない」は、ジャルジュ•ブラッサンのシャンソンによって大衆化した有名な詩である。この詩をめぐって、のちにフランシス・クレミュとの対話のなかでアラゴン答える。
「……この詩が書かれたのは一九四三年です。そこで歌われていることは、占領の不幸という事実に立って言われているのです。フランスの悲劇的な諸条件のもとで、どうして幸せな愛をもつことができたでしょう?……共同の不幸のなかでは幸福はありえない、というのが、当時この詩でうたわれた主題です。……ここでじっさいに提起されているのは、幸せな愛は可能か不可能かという問題ではなく、夫婦というものが可能か不可能かという問題なのです……」(アラゴン『F・クレミニとの対話』
国民が直面している共同の不幸を忘れるために愛のなかに逃避することはゆるされない。敵を眼のまえにして闘っている人たちにとって、幸福な愛はありえないのである。おなじような考えが「鏡のまえのエルザ」にも見いだされる。燃える戦火と仆れてゆく英雄たちを鏡のなかに見るエルザは、彼女じしん、たたかう英雄像として映し出されるのである。
アラゴンは『断腸詩集』(一九四一年)以来のレジスタンスの詩において、フランスの伝統的な韻律、脚韻をもった詩形を採用している。しかも、この詩における民族形式─定形詩の問題を、アラゴンはすでに第二次大戦の前夜に解決していたのであった。アラゴンは一九五四年の第二回ソヴェト作家大会における講演で述べている。
「……第二次帝国主義戦争前夜の一九三九年にフランス詩の諸問題が解決されていたということは、ナチス占領軍にたいするわがレジスタンスの活動家たちに、詩による援助と支持をあたえることとなり、それによって幾千幾万の愛国者が立ちあがり、かれらの戦列に加わったのである。……
定形詩の技法について討論するということはそれ自体、つまるところ若干の定形技法の使用をたがいに認めあっていることを前提とし、この討論を行なう人びとのあいだに共通の詩法がうちたてられることを前提とする。そうしてこの共通の詩法は、わたしがさきに語った、形式上の個人主義を否定することになる。つまり、ほかの詩人たちの経験を投げすてて、ひとりひとりの詩人にたいして自分だけの形式を創りだすように要求する、形式上の個人主義を否定することになり、詩人として評価されるためには、ぜひとも独創性《オリジナリテ》が必要だとする、現代の独創性崇拝を否定することになる。定形技法について討論することそのことが、数世紀にわたる詩人たちによって、いやひとり詩人たちだけでなく、詩人とその読者によって、辛抱づよく、永いあいだかかって鍛えあげられ、民衆によって受けいれられた詩形へと詩人たちを連れもどすからである。定形詩の技法について論ずることは必然的に、あの詩としての音楽的特徴を失い、民衆によって聞かれることもなく、民衆のこころにこだますることもない、常軌を逸した、個人的で、崩れた(自由)詩形を退け、詩人たちを民族的な詩の言葉へ連れもどし、人びとが書くことを忘れてしまった言葉へ連れもどすのである。いまや、全国民にむかって語りかけねばならないという問題が日程にのぼっているのである」(飯塚書店『アラゴン選集』第二巻二七四ページ)
ここには、詩における民族形式の深い意味が語られている。それを発展させることは、「詩における形式上の個人主義」にたいする闘いでもある。アラゴンのこの定形採用はしかし、作詞者の形式主義に逆戻りすることではなく、定形を新しく発展させ、詩のなかに音楽をとりもどすことでもある。そしてそれは、レジスタンスの時期の思いつきによるのではなく、長い研究による理論にささえられているのである。
戦後まもなく、ある批評家たちはレジスタンスの詩を歪曲し、黙殺し、抹消しようとし、そうすることによって歴史的なレジスタンスそのものにたいする攻撃をくわだてた。ジャン・ペリュという批評家は言う。
「〈レジスタンスの詩〉などというものはない。それは一九四〇年後の占領下に現われ、『解放』の翌日に占領とともに消えうせた、特殊な性質をもった詩の観念を言い表わそうとしたものである。それはフランス詩の歴史にあってはほんのつけたしのエピソードのごときものだ。純粋詩の表面に、歴史的な事件の渦巻きによって一瞬つくられた、いわばひとつのさざ波のようなものだ……」
レジスタンスの詩はこのような「純粋詩」に反対し、虚無や絶望の詩にたいする、文学的ペシミスムにたいする闘いの詩として生まれた。レジスタンスの詩は、祖国解放と自由のための闘いのなかで、新しい英雄たちの闘いに出会い、英雄たちのいさおしを叙事詩にうたった。こうして詩はたたかいのなかで「歌う武器」となり、敵にたいする強力な武器となることができたのである。
『フランスの起床ラッパ』は、ナチの圧制、虐殺、野蛮に抗して挙げられた、誇らかな人間の声であり、人間の尊厳と自由をもとめ、祖国愛をうたいあげた歌声である。それは孤独や絶望と闘う希望の歌である。
一九八〇年五月
(新日本文庫『フランスの起床ラッパ』 1980年6月)