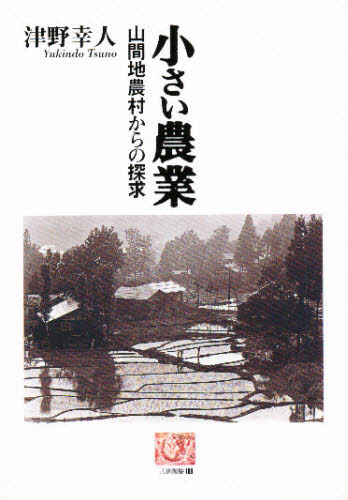![]()
わが師)農業は人間に内在する暴力性を飼いならす。労働三昧の功徳 #津野幸人 #小さい農業 RT_@tiniasobu
2023/04/27
敬愛する津野幸人(つの・ゆきんど)先生から、パソコン内の手紙を送っていただきました。
http://ankei.jp/yuji/?n=2456 にあるように、屋久島の方にうかがったことばと共鳴する大切なものがあります。
当時僕が満州で見た日本人のうち、中国人や満人に対して正直にやさしくしていた人は、さあ、一〇人のうち四人いたかなあ……。僕は、自分としては、一生懸命やさしく正直にしていたけれど、その仕方が足らんかったかな、と今になって反省しています。
ロシア兵が入ってきた時、日本人でもつねひごろ中国人にやさしくしていた人は中国人に隠してもらっています。その逆に、いつもひどい目にあわせてきた日本人の場合は、中国人たちがロシア兵に渡す前に自分たちで銃殺しましたね。
いくら日本人が頭を下げても、僕なんかの時代を生きた中国の人たちは、日本人が中国でしたあの仕打ちを死ぬまで忘れんですよ。
人種差別をなくしていって、将来は世界をひとつの家庭のようにしないといけません。僕は、満州で日本人のものすごい仕打ちを見てきたんですから。
(安渓遊地・安渓貴子 聞き書き、屋久島の雑誌『季刊・生命の島』25号より抜粋。)
〇自己に内在する「悪」への「反」
農文協・原田津(しん)さんへの手紙――「農家再訪」を読んで想う
津野幸人
戦後、続々と [愛媛県松山市の]
私の部落に青年達が戦地から復員してきました。彼らは私も軍人であったことを認め(最後の海軍予科練習生)、一人前に付き合ってくれました。(元々、幼馴染でしたが)。
彼ら、第一線で戦闘をした青年達の語る中国戦線での侵略・暴行の実態は、地獄絵そのものでした。これは若い衆のホラ話の要素も含んでいると想っておりましたが、記憶に鮮やかな話でした。その後、農林省試験場、大学農学部と職場を変えましたが、第一線経験者の語る生々しい暴行の実態は異口同音でした。
思えば、松山藩が親藩として第二次長州征伐に出兵したとき、山口県大島で、武士は略奪と婦女暴行をやりました。領主父子は維新後にこの罪を咎められたのですが、金十五万両を新政府に献金して罪を許され、のちに伯爵となりました。大金は領内の裕福な庄屋衆より徴収したもので、明治維新を理由に踏み倒されました。
官軍側の長州武士においても、会津攻めの際の略奪物件(懐中時計)を個人から見せてもらったこともあります。さらに、埼玉県北本宿では上野で戦った彰義隊の家族が、荒川を遡って船で落ち延びたとき、これを農民が襲って財宝を略奪しました。この財宝も私は実見しました。これらは秘匿しておくべきでしょうが、酒に酔った勢いで、心を許す者に漏らしたのでしょう。
各地の農村を回って想うのですが、概して戦争に強かった郷土部隊(四国、九州)に婦女暴行が多いようです。鳥取連隊は兵士が弱かったので、暴行の事件は少ないようです。
戦争に強かったと聞く東北農民とは、裏話を聞くほどの深い付き合いが無いのでこの種の情報はありません。原田さんは如何でしょうか。
このようなことをことさらに書き立てるのは、人間に内在する狂気(原罪)をどのように飼い慣らすか。これが農業の役割りで、労役三昧の功徳であるといつも考えております。
人間の狂気が農という行為で収まって、あたかも山中の湖面に山並みを映しているような光景を原田さんは描いていると、私は「農家再訪」を読んで想うのです。農家へのヴォリュームを上げた最大のエールを感じます。
農文協では東北の稲作農家の優良事例を紹介しています。一般に、これを生産技術が違うといってしまいますが、正確には技能の差であす。技術は、マニュアルとして一般化できるので普遍性をもちます。しかし、技能は個人の能力に帰属しており、文字で表現できないコツの要素を含んでいます。名人になればなるほど、労働量にはおかまいなしに手をかけます。もはや、彼にとっては農産物というよりは芸術品です。そして、この作品こそが、自分自身だという誇りをもっています。こういった誇りは、かつて稲の多収穫競作にもみられました。熱達した人は、稲作についての理論を身につけ、それを実践で確かめることによって、研究者にも劣らぬ学識を養っていたのです。こういった人に遇うと、まさに労働が自己を高めるとい
見本をみる思いがしたものです。有機農業の実践者のなかにも、思わず目を見張るほど立派な思想の持ち主がいます。自然秩序の認識にたった清々しい倫理観――これは裸の労働より得たものですが――と、完全に大衆社会を脱皮した叡知をもっています。
実際に農業をやる場合、生産性を無視した労働量を生産に投入することはできなません。が、そこには手順がいります。道具を使った裸の労働にまず徹底的に習熟し、そこから機械を駆使する段階へと移行することは認めましょう。これを省略すると、生命の躍動とじかに触れる感動を味わうことができません。柏祐賢[かしわ・すけかた、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%8F%E7%A5%90%E8%B3%A2]の言う「情熱からでた叡知なしに為される農業」に堕してしまうのです。情熱と叡知ある農業は、必ずや技能を伴います。また、これでなければ果たし得ない部分を含むところの個性的な生命倫理の段階に進むのです。これを指して、農民からみた「農業の発展」と呼びます。技術からは倫理は生まれません。誰しもが持っている悪を制御する反、つまりは
、生き物の命を貴ぶ技能によって具現できます。
右に述べた立場をとれば、「小さい農業」が充満する日本農業に明るい光明がさしてきます。小さい農業であるからこそ、多くの人が農業に参加でき、啓発的労働を楽しむことができるのです。ここで技能を研くことにより「地域に生きる誇り」が生まれてきます。こうした人が増えてこそ、地域社会は活き活きと光り輝いてくるのです。