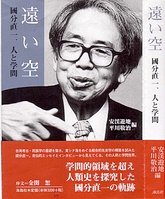![]()
新刊案内)『遠い空・國分直一、人と学問』(海鳥社)が出ます
2006/03/03
このたび、福岡の海鳥社から、『遠い空――國分直一、人と学問』という本がでま
す。2005年の1月11日に亡くなられた國分先生の学的自伝を第一部とし、とっ
ておきの語りを第二部として、略年譜をそえました。
先生のお若いころの写真も満載です。
先生から「若い友人」と呼ばれる光栄に浴した、安渓遊地と平川敬治さんが編集し
ました。序文は、著名な考古学者の金関恕先生です。
3月16日に出版になります。
安渓あてに注文してくだされば、定価3200円+税のところ、2割引になります。
1冊2688円です。国内送料は、1冊が210円、2冊以上まとめてくだされば、
送料無料となります。
ご注文は、メールでyama@ankei.jp あてにお願いいたします。
序文(校正前のものですが)をご参考までに掲載しておきます。
序
大阪府立弥生文化博物館館長 金関 恕【ひろし】
私たちが尊敬し敬慕する國分直一先生が二〇〇五年一月一一日に九六歳の生涯をと
じられた。満身学問に対する情熱にあふれ、しかも常に謙虚なお人柄であり、若輩の
声にもよく耳を傾けてくださった。たとえ一つの小さな謎であっても、それを解くた
めにはどのような苦労をもいとわれることがなかった。いや、苦労ではなく、先生に
とってそれが大きな喜びであった。野外調査にお供をして心を打たれたのは、たぎる
ような暑熱も身の凍る酷寒をも苦にされる様子がなく作業に集中しておられたお姿で
あった。その先生が、四一歳までの、いわば前半生を回顧した肉筆の記録を遺されて
いる。先生に親炙する方々がこれを読み解き、これを柱に先生の生き生きした語りを
加え、一冊にまとめて出版されることとなった。このような労をとられた安渓遊地さ
んや平川敬治さんの、たっての要請で私が序文を書かせていただく。先生の自伝に序
文を書くという、そんな僭越なことが許されるだろうか。しかし顧みると先生と私た
ち一族は親子二代にわたる厚情に結ばれている。家族にとって特別なお方である。あ
えて無礼を犯すことにした。
人類学者として、台湾の原住民族や華人の形質や系統に強い関心を持っていた父の
金関丈夫【たけお】が、國分先生と初めて調査をともにしたのは、一九三九年に行わ
れた西南部の二層行渓南岸・大湖遺跡の発掘の折であり、父は先生に捧げられた古稀
記念論集の序文に「当時気鋭であった博士の、台湾先史学,民族学に対する熱情に触
れ、同志を得た思いでありました」と書き記している。以来、先生と父は深い友情に
結ばれ、台湾でも日本でも幾多の共同研究・共同調査を行った。父が急死したとき、
山口から我が家に駆けつけてくださった先生が大声で哭泣しておられたのを昨日のこ
とのように思い出す。葬儀の手はずに心を奪われ、先生のように天真に声を挙げられ
なかった私を情けなく感じたものだった。
敗戦とともに、台湾に在住していたほとんどの日本人は故国に引き揚げた。しかし
少数の学者・技術者たちは、中華民国台湾省として発足した新政府の要請により、数
年間在留し、研究・教育・技芸の仕事を援けた。著者の國分直一先生も父も四年間滞
在し、台湾考古学、人類学、民俗・民族学の調査研究を続行した。國分先生の活動の
成果は報告や論文として次々に発表されているが、おもに考古学関係の初期の業績は
『台湾考古誌』(一九七九年)や『台湾考古民族誌』(一九八一年)にまとめられて
いる。前者は譚継山氏によって漢訳され「光復前後先史遺跡考證」の副題付きで台北
市の書肆から刊行された。現在、大発展を遂げている台湾考古学界でも、学史をたど
るための必読書に数えられ、読み継がれている。後者には、おそらく先生にとって最
初期の論文だと思われる「小岡山発見の先史時代遺物」(「民族学研究」第五巻五号、
一九三九年)が挿図を改訂して収録されている。また、「東洋史研究」(第一一巻一
二号、一九五一年)に掲げられた「戦後台湾における史学民族学界――主として中国
内地系学者の動きについて」という記録も収録されている。これは、日本領有時代、
国民党政府による接収の時代、今では外省人とも呼ばれる有名な考古学者の来住の時
代という移り変わりによって、新しい学界が形成される過程を学ぶ上に極めて貴重な
記録である。
國分先生は、戦後の最初の間は台湾省立の編訳館に所属された。多くの目的をもっ
た規模の大きな機関だったという。その目的の一つに台湾研究があり、「日本文化の
接収を目指して翻訳陣を強化するとともに、日本時代の研究の未完のものはこれをあ
る程度迄完成せしめて、その成果を学界に提供せしめようとする意図のものであった」
という。しかし、一九四七年二月二八日の政府に対する反乱事件(二・二八事件)の
後、編訳館は改組され、先生は台湾大学民族学研究室に移られた。大学では考古学・
民族学を志す陳奇禄、宋文薫教授など、今では世界的な学者を育てられた。一九八三
年、私が北京の学会でお会いした張光直教授も「國分先生の講義を受けた」と語って
おられた。教育の上でも大きな功績を果たされたわけである。
國分先生はご家族を先に帰国させ単身で残られた。私たち家族も長男と次男の私が
早々に帰国した。先生は父母と三男の悳【とく】の住む家に同居された。私の頼みで
弟が書き綴ってくれたその当時の思い出がある。別に発表の機会をえたいと思うが、
先生が如何に集中して仕事に励まれたか、どれほど夫人を愛しておられたかという話、
二・二八事件のとき南部の民俗調査から命からがら逃げて台北に帰られた話などが語
られている。また、食べ物、飲み物、嗜好品、音楽などの趣味、おしゃれなどの一切
に興味がなく、「全身全霊を研究に集中できる人は見たことがない」という趣旨の父
の感嘆も伝えている。ただ例外は映画であったという。戦後の台湾在住中は、弟を連
れてよく映画館に行ってくださったらしい。「國分先生の生涯であれほどしばしば映
画を見られたことはないと思う」と記している。私も先生と映画談義などした覚えは
ない。弟とのこうした付き合いがあったせいか、その後も弟とはよく文通しておられ
た。後に(一九九六年)評論家の川村湊氏が著書『「大東亜民俗学」の虚実』の中で、
戦争の中で刊行された雑誌『民俗台湾』への誤解に基づく酷評を発表した。父ととも
にこの運動を推進した先生からの反論が本書に収録されているが、学術的な筆致の中
に先生の押さえきれない怒りが伝わってくるようである。
國分先生が父の家に同居中、父は、帰国されたご夫人宛に「國分先生行状絵巻」と
題する戯画入りの書状を届けた(前記『台湾考古誌』収載)。その最後に、「國分先
生は何一ついけないところのない人ですが、ただ一つ遠慮深いので困ります」とあり、
勉強に夢中になって夕食時間に遅れ、手数をかけるまいと、外食のために自転車で町
の方に出かけられ「遠慮した罰があたって自転車もろともドブの中にスッテンコロリ
とはまってしまいました」とふざけている。たぶん実話であろうが、先生は九〇歳を
超えても健康と体力に自信を持ち過ぎて買い物にも自転車で出掛けられた。他人に迷
惑をかけることを極度にさけられた。それが入院の原因になってしまった。先生の晩
年、私は何のお世話もできず、今、後悔と罪悪感にさいなまれている。
本文にあるように、半生記の書かれているこの「回覧雑誌」は、台湾から帰国後長
い間、父の手許にあり、死後に國分先生にお届けした。私には読む機会があったわけ
だが、手書きの記録に抵抗を感じて食指が動かなかった。この度あらためて拝読し、
ご自身のことをあまり語られなかった先生のお人柄が強く胸を打った。懐かしい台湾
の風物の中で展開する先生の半生が生き生きと伝わってくる。特高につけねらわれる
くだりでは手に汗を握る。何という清らかな正直なそして偉大な人なのだろうか。高
潔な道徳観と美しい繊細な思いやりを持った先生のような人には、老い先の短い私の
人生ではもう二度と会えないような気がしてならない。
かなせき・ひろし一九二七年京都府生まれ。京都大学大学院修了。天理大学名誉教
授。著書に『弥生の習俗と宗教』(学生社,二〇〇四年)ほか多数。